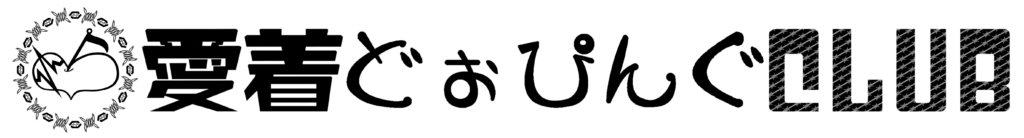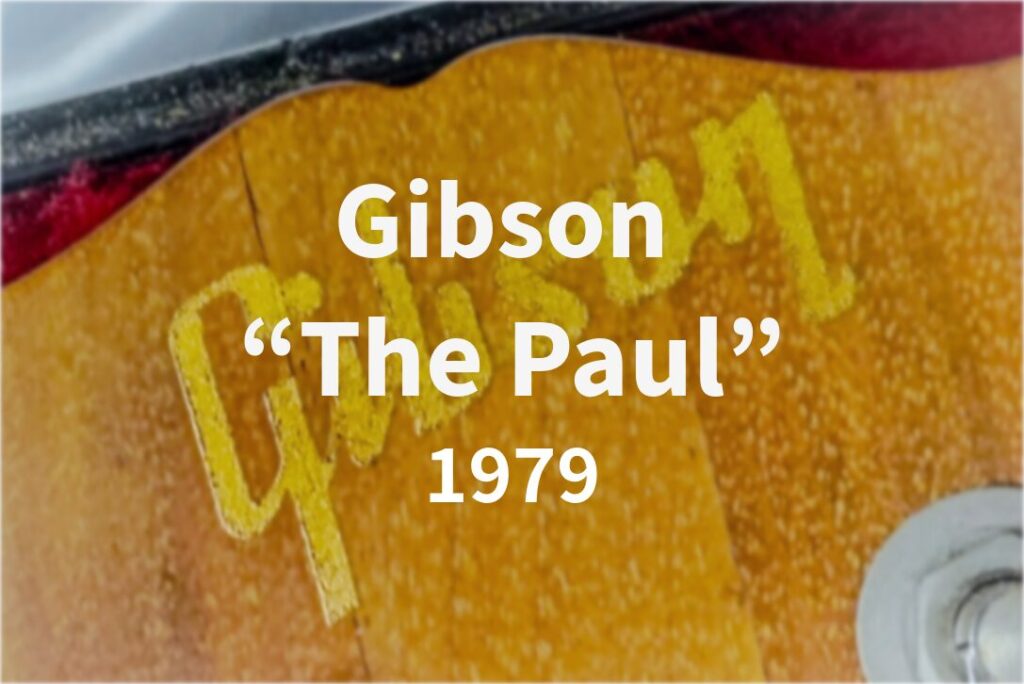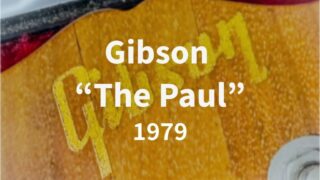Gibson The Paul の魅力とスペック|70〜80年代Norlin期に生まれた“必然の銘器”
第2章:構造・素材・思想──異端仕様に滲む合理性
後述しますが、以下は“The Paul”の基本的な仕様。
- ウォルナットネック&ボディ
- エボニー指板
- ラージヘッド
- 突板なしヘッドストック
- ボリュート
- ドットインレイ
- バインディング無し
- ボディコンター
- セットネック
- ナチュラルフィニッシュ
- オープンピックアップ
参考個体
今回紹介するにあたり参考にした“The Paul”は、シリアルナンバーから1979年製の個体と判断。
POTデイトやピックアップ裏は未確認です。
年式により微妙に仕様が異なるかもしれませんので参考程度に。
※当個体は、エスカッションとストラップピンを交換しています。サドルとトグルスイッチのキャップ(クリーム→黒)も変更したかもしれません。

廉価モデルとして誕生した“The Paul”。
作業面でコスト削減とみられる仕様もありますが、使用されているパーツ類は廉価ではありません。
そして、廉価モデルだからと作業工程を減らすことが、必ずしも楽器としてデメリットに働くとは限らないかもしれないことを、“The Paul”のもつ魅力から伝えられればと思っています。
The Paulの秘められた可能性
ボディシェイプ自体は、ノーリン初期1974年頃に発売された姉妹機“S-1”や“マローダー”から、末期1986年の“SONEX180”や“invader”まで引き継がれており、ノーリン期を代表する型の1つと言えます。
この型で使用されている素材は、アルダー・メイプル・マホガニー・ウォルナット・マルチフォニックと様々です。

ボディシェイプ以外で、この型のほぼ全てに共通する、最大級に驚愕的な特徴として、ネックのジョイント方法が挙げられます。
この型は、従来のGibson社の伝統であるセットネックではなく、ライバルFender社の特徴ともいえるジョイント(ボルトオン/デタッチャブル)ネックの仕様を採用しているのです。
流行もあり、この節操がなく映ってしまうところがノーリン期特有の違和感を象徴しており、こういった点の積み重ねが賛否の割れるところでもあり、好きな人には狂おしいほど堪らない要素であるのかもしれません。
コスト削減と合理化、Fenderユーザー層の取り込み/新規開拓といった狙いはもちろんのこととは思いますが、私はこの型に関して、木材の選定や仕様を吟味する「実験素体」の側面もあったのではないかと考えています。(根拠はありません)
“The Paul/The SG”は、高級材とされるエボニーとウォルナットで製作されています。
ボディ&ネックにウォルナット、指板にエボニーといった構成は、おそらくGibsonのエレキギターでは後にも先にも存在せず、他社でも限定的にしか作られていないような異端の仕様です。
“高級な木材”が使用されていることに目が行きがちですが、この組み合わせはベースではよく見かける構成であることを踏まえると、明らかに狙った音のある、目的を持った選択であると考えられます。
勉強不足なだけかもしれませんが、同時期に発売されたGibson製のベースにこの構成がないのが逆に不思議なくらいです。

さらに、このボディシェイプで唯一“The Paul”だけが“Gibsonらしさ”の象徴であるセットネック仕様の王道スタイルに戻されたことを考えると、Gibsonは“LesPaulの系譜”として、ひとつの完成形と位置付けたのではないでしょうか。
都合のいい解釈で、愛情の暴走が論理破綻から目を逸らしていますが、何か確信めいたもの、勝負に打って出る試金石的価値や、内に秘めた覚悟といえるものがあったのではないかと、思いを巡らせてしまい魅力を感じずにはいられません。
邪推と希望的観測と自問自答にまみれていますが、そのような直感的なものが自分自身の価値基準・判断基準だと信じてやまない当サイトです。
“Standard”はマホガニーが安定供給され始めるまでの繋ぎの期間だけの仕様なので、割に合わなかったのか、マホガニーのほうが汎用性の高い音/優れた音と判断したのか、単なる思いつきか、当時の成否の判断はわかりかねます。
ただ実際に触れてみると、スチューデントモデルであっても、根底には“バースト”や“custom”といった“音”を意識した明確なイメージや、“道具”としての設計思想をもち、目指すべき方向性を模索するクラフトマンシップを感じられるギターと言えます。
他社ウォルナットボディ
以下は、ウォルナットボディをもつエレキギターを製造したことのあるギターメーカー。
モデル名・型番は不明なものあり。
- Fender :stratocaster・telecaster
- PRS:CUSTOM24・Private Stock・Employee guitar・SE CUSTOM
- Rickenbacker:330W・360W
- Bill Lawrence:BT2/BT2E
- SCHECTER USA
- KAY:titan
- ARIA ProⅡ
- MOON
- Deviser
※『ウォルナット“カラー”』という塗装のギターが多く存在するので、混同なさいませんよう。
個性を最大限に発揮する塗装
ウォルナットボディの“standard”は、基本的に“アンティーク・ナチュラル”カラー一択で、仕上げは、“サテンフィニッシュ(艶消し)”と“グロスフィニッシュ(艶あり)”の2種。
カタログなどの資料は手元にないので思い込みですが、初期製造分は、上記画像のような極薄ラッカーの“艶消し”ナチュラルカラーだけで、“艶ありのアンティーク・ナチュラル”は“deluxe”発表後の80年製以降に加わった仕様だと思われます。
“Firebrand”以降は、“deluxe”で採用された“silver burst”や“gold burst”を吹かれた“イレギュラーなstandard”も稀に存在するようです。
ギターに施される塗装の目的は、主に“美観”と“木材の保護”ですが、ここにもコスト削減・作業工程の削減の節が見られ、出荷に際しての保護だけを目的としているのではないかと思えるほど、最低限平滑になる程度の極薄ラッカーで仕上げられています。
私は、楽器には「音を発生させる装置」と「音を奏でる道具」の2つの観点があり、音は両側面からアプローチしたトータルバランスであると考えています。
指の摩擦だけでエスカッション周辺の塗装が剥げたとみられる個体が中古市場に多数出回るほど、ダメージに弱いデメリットはありますが、「楽器本体の材質は音と関係し、(厚い)塗装は楽器元来の音質を阻害する」という説を支持するなら、道管を感じられるほど薄い塗装は、塗膜による音質への影響を極力抑えることに繋がります。
つまり、ただでさえ『レアなウォルナット&エボニーという個性を最大限感じることができる』のです。
音質改善を謳いリフィニッシュや塗装を剥ぐなどの強引な手法もあります。
入門用新品激安ギターのように木材の素性がわからない場合は、逆に分厚く硬い塗膜で固めるほうが出音に対してメリットがあるかもしれません。
ノーリン期の品質低下を問題視する声もありますが、手間と時間と心理的負担のかかる塗装作業を軽減し、尚且つ音が良くなる結果に繋がるのなら、最初から「最低限のことだけで、余計なことはしない」という選択も結果的には素晴らしく理にかなっていると言えます。
「自分の音」以外に正解はありませんし、この文章自体が私以外には「他人の意見」でしかないので恐縮ですが、生鳴りを含め、弾き心地から受ける印象は、土台がしっかりとしており、鈍器を堅いものに叩きつけるような直線的に前方へ向かう音だと感じます。
※ここで言う「生鳴り」は、「アンプに繋がない弦だけの音」
【広告欄】Gibson The Paul
最低限の極薄塗装ということもあり、どこかアンティーク家具のような雰囲気を醸しています。
そして最低限の極薄塗装ということもあり、同じような場所の塗装が剥げている個体が多くみられます。
S©ALETONE.のひとりごと
あまりにも長くなってしまったため、記事を8つに分けることにしました。
次回、第3章は「ボディ」に重点を置いた回。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。
どこかの章で、あなたの琴線に触れることができたなら──それだけで十分です。
広告欄
※このリンクにはアフィリエイトが含まれています。内容の確認はしておらず、紹介や推薦を目的としたものではありません。

ご利用いただくことで、運営のささやかな支えになります。判断はご自身の意志でお願いいたします。