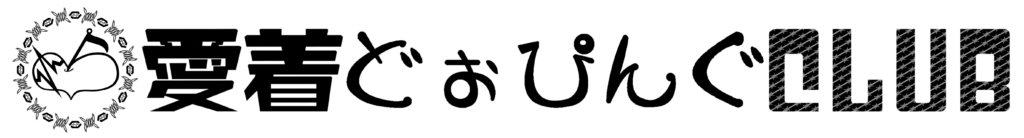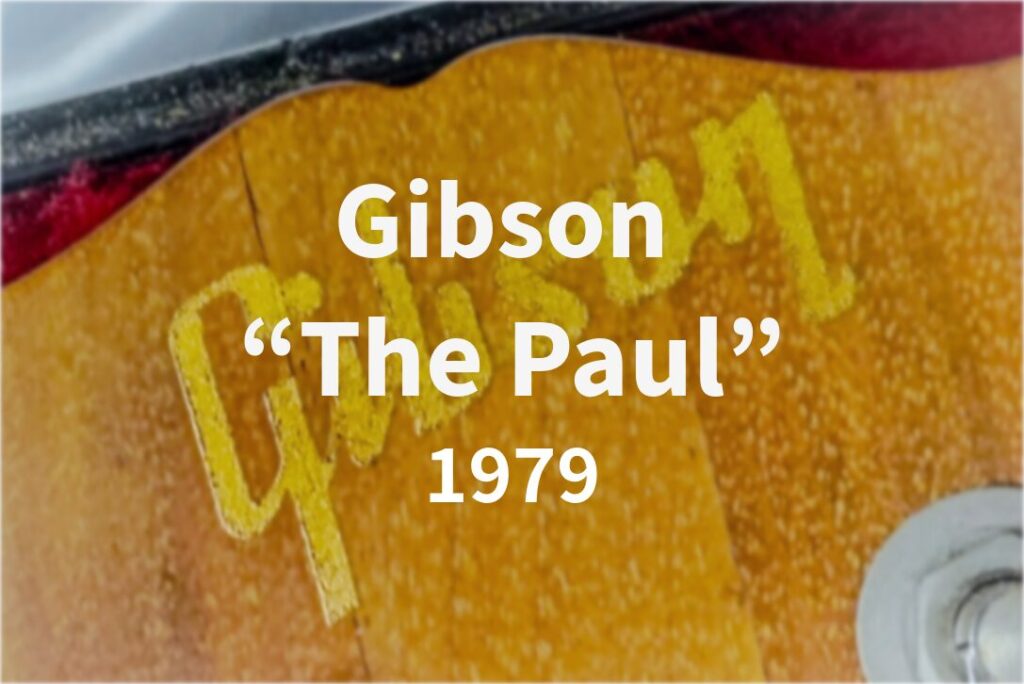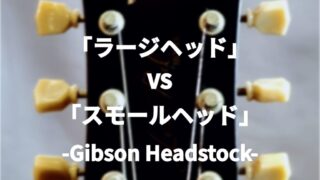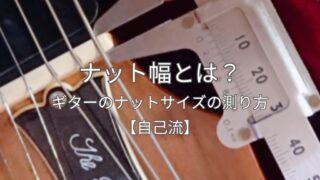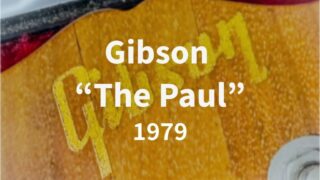Gibson The Paul の魅力|70〜80年代Norlin期に生まれた“必然の銘器”
第6章:ヘッド編──ヘッドストック形状とギターチューナー
- デカヘッド
- トラスロッドカバー
- ロトマチック
- Grover製マシンヘッド
- キー・ストーン
ヘッドストック
形状
Large Head Stock
先述のとおり、ノーリン期の特徴である「ラージヘッド」仕様。
ラージヘッドはノーリン期に“統一規格となったこと”が特徴として広く知れ渡っています。
しかし私の記憶違いでなければ、ダイヤモンド・インレイに目を奪われ、バインディング・マジックで見落とされがちですが、実は既に「1954年製“Les Paul Custom”」の時点で上位機種の象徴としてラージヘッドは存在していたはずです。
“Gibson Les Custom”の検索結果
あまりヘッドストックに使う表現ではないけれど、分割線から“3Pネック+両サイドの耳貼り”の5ピース。

個人的に“ラージヘッド”の呼称はFenderのイメージで、Gibsonの場合は“デカヘッド”と呼ぶ印象を持っているのですが、どこから影響を受けたのかは自分でも謎。
オープンブック・ヘッドストック
Gibsonの特徴の1つでもある、本を開いたような左右対称のカーブを描く「オープンブック・ヘッドストック」

ヘッドストック【表面】
突板(化粧板)なしのヘッドストック。
Gibsonのエレキギターで、オープンブックのヘッドトップに黒い化粧板が貼られていないモデルは珍しいかもしれません。
後継機「deluxe」になると“Firebrand”であっても突板の貼られたものがあります。
※この記事を書くまで気にしたこともなかったですが、突板を貼らず「黒い塗装」の可能性もあります。
※以下は、レギュラーラインの黒い突板。

Gibsonロゴ
この個体はゴールドのロゴ。

80年製造の“Firebrand”シリーズからは“Gibson”ロゴが彫り込まれた焼き印(風)仕様になるのですが、私はウォルナットボディに焼き印ロゴの“Firebrand”The Paulをあまり見たことがありません。
※“The Paul”の話ではありませんが、ロゴの字体は年式により特徴があるそうです。
トラスロッドカバー
- “The Paul”刻印入りの専用仕様。
- 複数パターンあり。
ナット幅
42~43㎜
machine-head
“The Paul”ではナット・ワッシャーで固定する「ロトマチックタイプ」が採用されています。(後述)
machine-headの配置
配置は「L3:R3」
※上記画像“Gibson デカヘッド”を参照。
立てかけた状態のヘッドストック・トップ面、向かって…
- 向かって左側を【L】:「Left」・右利き用のギターの場合、低音弦側(4~6弦)
- 向かって右側を【R】:「Right」・右利き用のギターの場合、高音弦側(3~1弦)
…と表記するのが一般的。
取り付けの際は、弦の通す穴径に違いをもたせている場合もあるので注意が必要です。
(セット販売ならシールなどが目印)
ヘッドストック【裏面】
シリアルナンバー
シリアルナンバーより、1979年製。

「NIHON GIBSON」シール
「NIHON GIBSON」のシールは、為替が大きく変動した時代ということもあり、個人輸入・並行輸入品が横行したため、代理店を通した“正規輸入品”であることの証明なんだそうです。

このシールは、剥がすにしても残すにしても汚く残るようで、綺麗に剝がそうとすると溶剤を使用しないといけないらしく、極薄塗装に対してなら尚のこと一層如何なものかと考えあぐねています。
Machine-head/ペグ
ヘッドストックをナットで挟み固定する“ロトマチック”タイプが採用されています。
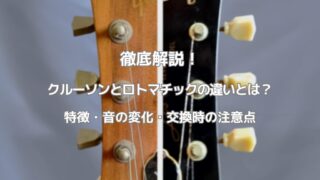

「“vintage type”に比べると重量があるので音がタイトになる」と言われていますが、それに加え、締め付けによる地盤(木材)の密度の変化も影響しているかもしれません。
ボディを強めに肘で挟み込み、ボディの振動を抑えると、音質が変わる(気がする)ように。
ペグの呼称
日本では「ペグ」のほうが一般的な呼び方ですが、正式には「Machine-head/マシンヘッド」や「Tuner/チューナー」
“チューナー”だと“音叉”と混同しますし、あえて使い分けるなら、当サイトでは以下のような認識です。
正直『ペグ』でいいとは思ってますが。
- 本体総称:マシンヘッド
- 回転するつまみ:ペグ
- つまみ部分(パーツ):ペグボタン
- つまみの形状:キーストーン・オーバル など
クルーソン “vintage style”(上画像“黒い突板”)に比べて、ペグポストの背が高いのも特徴です。

Key-stone
ペグボタンが金属製のトライアングル・キーストーンで、個人的に大好きなポイント。
この時代のレスポールカスタムには手巻きハンドルが付いたバージョンもあったりして、見かけると気分が上がります。

リプレイスメント・パーツはGibson純正でも販売されているようです。(2025年6月時点)
改造目的で、近い形で妥協・本体無加工(ポン付け)・シャーラー(後述)互換・その他機能追加、など選択肢を広げるなら「GOTOH/後藤ガット」製で探すのが手早いと思います。
GROVER【Milk Bottle】
この個体のペグはGrover製のものが取り付けられています。

シャフト部を覆うカバーの形状から、通称“ミルクボトル”と呼ばれるこの年代の特徴。
グローバーより復刻されているようです。(型:102/カラー/V)
(2025年6月時点)
「GIBSON」刻印入り/Schaller M6/メタル・トライアングル・キーストーン
工場によるのか年式によるのかはわかりませんが、ロトマチック・“Gibson”刻印入り「シャーラー M6」仕様の個体もあります。
こちらもペグボタンはメタル・トライアングル・キーストーン。
ネジ穴の位置は水平。

※M6のネジ穴位置は大別すると3種類あるので、サイズ確認は勿論のこと、交換の際は注意が必要です。
※トライアングル・キーストーンは現在のラインナップにはない仕様のようです。(2025年6月時点)
【広告欄】Gibson The Paul
生産終了から40年。めっきり玉数も減ってきました。
ウォルナット・1ピースボディ・焼き印ロゴ・ミルクボトル、尚且つ美品の5拍子が揃った “The Paul” に出会うことは今後果たしてあるのだろうか?
S©ALETONE.のひとりごと
あまりにも長くなってしまったため、記事を8つに分けることにしました。
次回、第7章は「ネック」に焦点を当てた回。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。
どこかの章で、あなたの琴線に触れることができたなら──それだけで十分です。
広告欄
※このリンクにはアフィリエイトが含まれています。内容の確認はしておらず、紹介や推薦を目的としたものではありません。

ご利用いただくことで、運営のささやかな支えになります。判断はご自身の意志でお願いいたします。