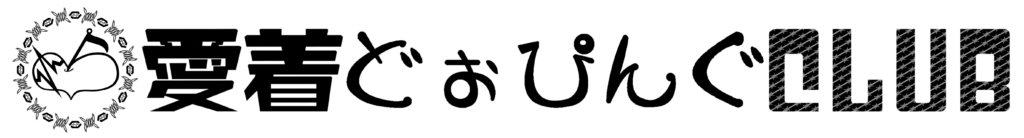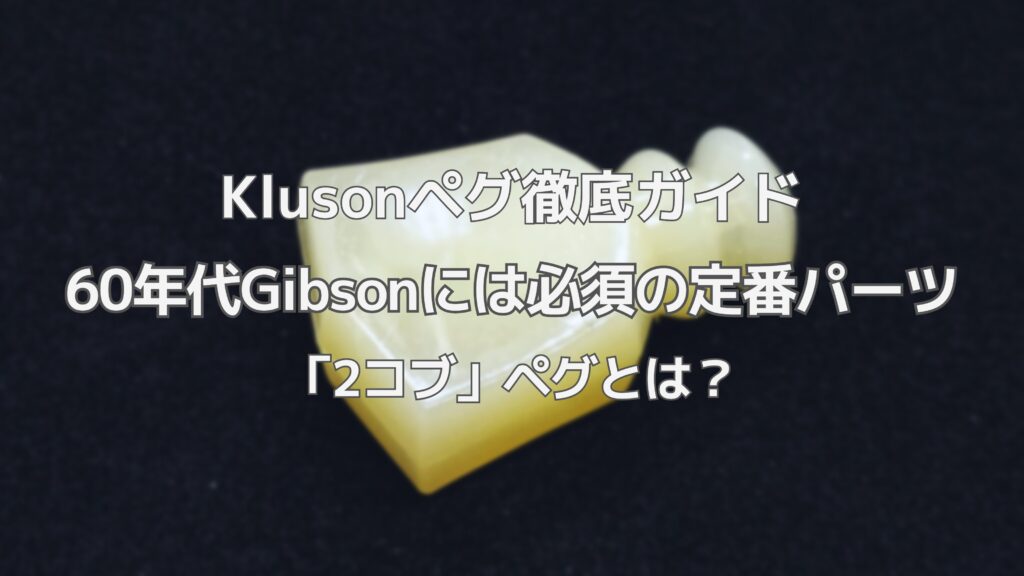クルーソン関連|ギターペグの仕様紹介・完全メンテナンス&修理ガイド
ギターの音や雰囲気って、意外と細かいパーツで変わるもの。
そのひとつが「Kluson “2コブ”ペグ」。1960年代のGibsonギターに使われていた、今ではあまり見かけない仕様のペグです。
見た目はレトロで、音にもほんのりヴィンテージらしさが加わる——そんな魅力を持っています。
「ペグってチューニングするだけじゃないの?」と思うかもしれません。でも、細部にこだわることで、ギターの表情はぐっと深まります。
今回は、“60年代Gibson再現の定番”である「Kluson 2コブペグ」をすこし解説していきます。
(使用画像は、Gibson刻印の後期型、70年代仕様ですが)
Kluson 2コブペグの特徴
Kluson(クルーソン)は、ギター好きにはおなじみの老舗パーツメーカー。特に1950〜60年代のGibsonやFenderに純正採用されていたことで知られています。
「Kluson 2コブペグ」とは、ヴィンテージギターに使われていたKluson(クルーソン)社製のチューニングペグ(糸巻き)の一種で、特に1960年代後半から1970年代初頭のGibson製ギターに多く採用されていたスタイルです。
「2コブ」「ふたこぶ」とは?
キーストーン型ペグボタン(ツマミ部分)のバリエーションのひとつ。
正式には「Double-Ring/ダブル・リング」といわれる仕様です。
キーストーンの根元にリング状の造形が2つあることから、通称「2コブ」と呼ばれています。
現在のカタログでは「DR」で表記。
キーストーン型には3種あり、他に「シングルリング」と「メタルボタン」があります。

このペグは74年頃の個体から取り外された後期型なので「“KLUSON” DELUXE」ではなく「“GIBSON” DELUXE」刻印。
2列刻印
「Double-Line/ダブル・ライン」
60年代はギアカバーに「KLUSON」「DELUXE」と2列で刻印されているタイプ。
現在のカタログなどでは「DR」表記。
(“DL”ではなく?)
対となる言葉は「シングル・ライン(SL)」
他に、1952年中期〜1956年頃に使用されていた、刻印の無い「No Letter」も代表的。
軽量構造
ロトマチックペグに比べて軽く、ギターのヘッド落ちを防ぎ、倍音豊かなサウンドが得られるとされています。
艶のある飴のような樹脂製ボタンは、見た目も柔らかくレトロな印象です。
重量

重量:約22.6g
ちなみに、シャーラー製ロトマチック・タイプは、1つあたり40グラム前後です。
↓詳細は過去記事で。
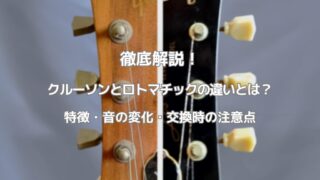


ポストの「へそ」
ベースプレート裏にはパテントナンバー。
(黒ラベル下:シリアルではないので、伏せる必要はないかもしれないけど)
年代によりペグポスト先端に「へそ」があります。

シャフト
年代によりシャフトが短い(ペグボタンの奥まで刺さってる?)ものがあります。
ヴィンテージギターとの相性
GibsonのSG、Les Paul、ES-335など、主に1964〜1969年頃のモデルに標準装備されていたため、復刻モデルや改造にも人気です。
(モデルによっては、同時期に「1コブ」や「メタルボタン」タイプも混在していたそうです。)
ギア比はやや粗めで、現代の高精度ペグと比べるとチューニングの繊細さでは劣ります。
しかし、その作りのゆるさ、いわゆる「遊び」からくる音の“揺らぎ”を好む人も多いようです。
拡大解釈ですが、効果としてはハードテールに対する“トレモロ・スプリング”のような感覚かもしれません。
このペグは、現在の量産ギターにはほとんど使われていませんが、ヴィンテージ再現やルックス重視のカスタムには欠かせない存在です。
見た目の雰囲気だけでなく、音のニュアンスにも影響を与えるため、こだわる人ほど選びたくなるパーツと言えるでしょう。
Amazonでの検索結果:“クルーソン ペグ Aging“