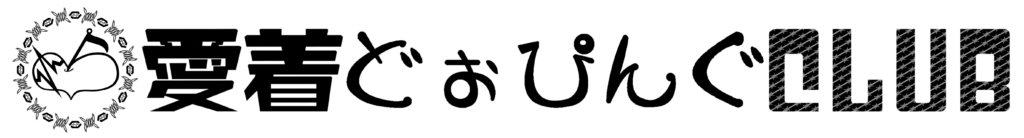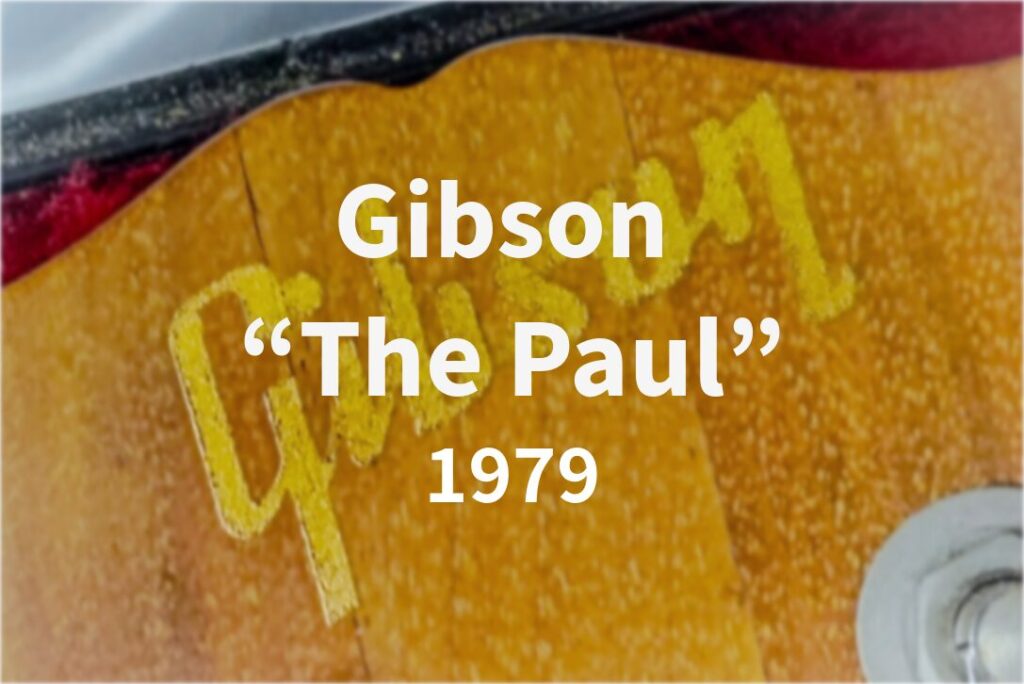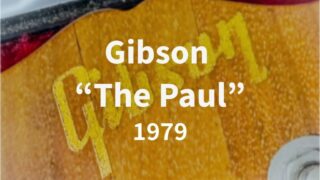Gibson The Paul──構造に宿る思想と、音に残る時代の記憶をたどる
はじめに
1970年代後半に登場した「Gibson The Paul」は、ウォルナット材や異端仕様で知られる名機です。
本シリーズでは、その構造・素材・音響・設計思想を徹底解説します。
ノーリン期ギブソンの魅力を深く知りたい方、The Paulの購入を検討している方、
そして“ヴィンテージ”の枠に収まらないギターの価値を探る方へ。
第1章:Gibson The Paulとは?70年代Norlin期の名機を徹底解説
Gibson The Paulの誕生背景、ノーリン期Gibsonの特徴とモデルの位置づけ、基本仕様を網羅的に紹介。
第2章:構造美と素材構成|ウォルナット×エボニー、唯一のセットネック
異色の素材選定と、同ボディ形状で The Paul にのみ採用されたセットネック構造の魅力を解説。
第3章:ボディ構造と設計思想|コンター加工・重量バランス・ハードウェア配置
演奏性と音響特性を両立するための設計思想を、具体的な構造から読み解く。
第4章:アッセンブリー構成|PAF・T-top・オープンPUの音響設計
ピックアップ構成や配線仕様から、The Paulの音作りの方向性を分析。
第5章:音響仮説(ボディ編)|ウォルナット材の響きを探る
SⒸALETONE.による独自の音響仮説。材質と構造が音に与える影響を考察。(未定)
第6章:ヘッドストックの特徴|ラージヘッド・ロトマチック・NIHON GIBSONシール
ノーリン期らしい意匠と、日本市場向け仕様に見られるディテールを紹介。
第7章:ネックとフレットの仕様|エボニー指板・フレットレスワンダー
演奏性に直結するネック構造とフレット仕様を、実用と思想の両面から解説。
第8章:Firebrandシリーズとの関係とまとめ|純正ケース・後継モデル
The Paulの終焉とFirebrandシリーズへの移行、純正ケースや付属品の情報も網羅。