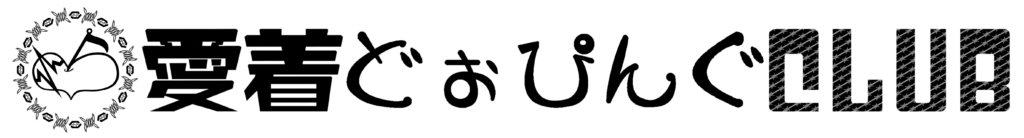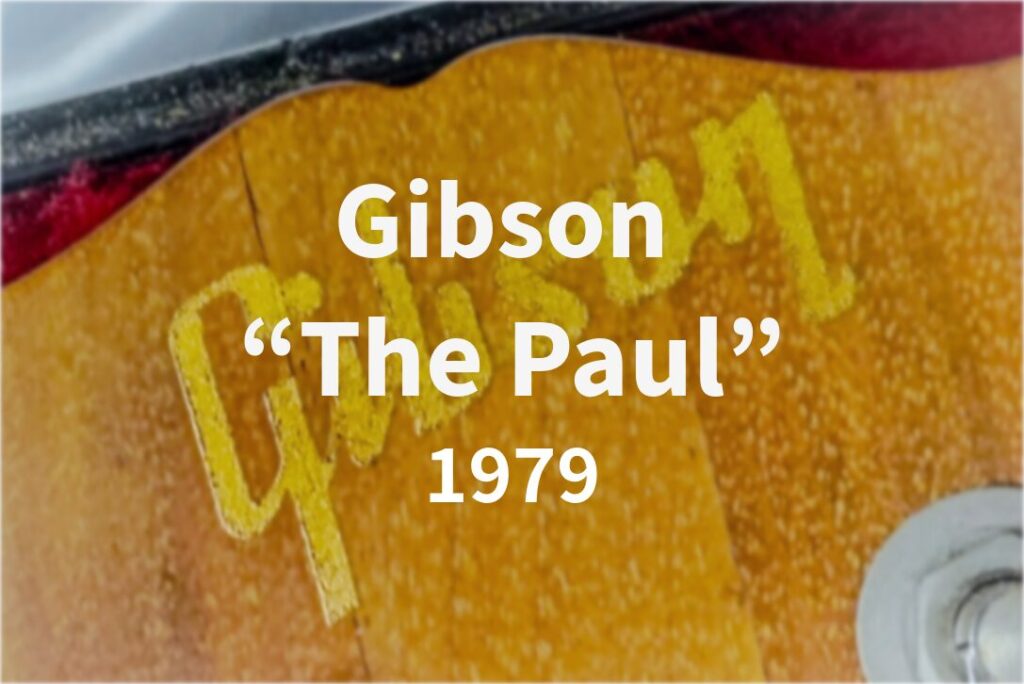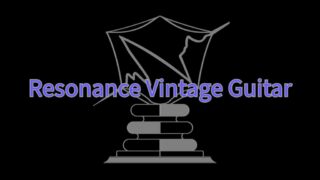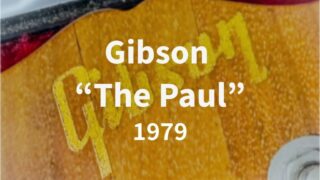Gibson The Paul の魅力|70〜80年代Norlin期に生まれた“必然の銘器”
第8章:最終章──Firebrandとロケットケース~まとめ
全8章に渡った「Gibson “The Paul”」の記事もいよいよ最終回。
この章では、80年頃を境に新シリーズとして確立された“Firebrand”と付属品のロケットケースについて紹介します。
ここまでお付き合いいただいた奇特な方が実際いらっしゃるのかはわかりませんが、辿り着いていただけただけで、ありがたいものです。
Firebrand
Firebrandシリーズとは
「Firebrand」は81年から新たに加わったシリーズで、意味は「火種」や「扇動者」。
The Paul・The SG・335-sと、その“Deluxeモデル”に付けられた名称で、特定の形状(Les Paul)/カテゴリー(ES)/グレード(special)で区別するよりは、「総合的な“仕様”」に対して付けられている印象です。
一時“V”や“explorer”も発売された“melody maker”のような括り。
Firebrandシリーズの特徴
当初は突板なしのヘッドストックに“Gibson”ロゴが彫り込まれた焼き印(風)仕様でしたが、The Paul Deluxeでは“Firebrand”を冠していても、レスポールの廉価モデル同様の黒いヘッドにゴールドのデカールを施した個体もあったりします。
仕様の差異が判然としないので、トラスロッドカバーにある“Firebrand”の刻印が目印。
ウォルナットボディに焼き印ロゴのThe Paul(Standard) “Firebrand”も稀に存在するようです。
ただよく見かける、焼き印ロゴでナチュラルカラーの“Firebrand”のほとんどは、マホガニーボディの「The Paul “deluxe”」に黒ペンキの飛沫を散らしたようなものである気がします。
Deluxe
The 〇〇 Deluxe
Deluxeでは、ボディ&ネック材はマホガニー材が採用されています。
リフィニッシュでなければ、カラーバリエーションは豊富。
トラスロッドカバーの刻印には、“LP Firebrand” や“The Paul deluxe”など複数パターンありますが、そもそも“deluxe”と“Firebrand deluxe”の違いが年式以外にもあるのかすらわからないので、同じものと認識しています。
ヘッドストックとブランドロゴは、突板なしに焼き印風ロゴ。もしくは、黒いヘッドトップにゴールドロゴ。
カラーバリエーション
フィニッシュ・カラーについて、以下はカタログ情報でもなく、私が“The Paul”を探し回っていた時に出会った、S-1/marauder‐The Paul/deluxe/firebrand‐sonex-180/invader/GK-55あたりの混同した記憶だけが頼りなので参考程度にしてください。
基本となるナチュラルはいずれもアンティーク家具のような、極めて薄い塗装でした。
- アンティークナチュラル(艶消し)
- 艶ありナチュラル
- ナチュラルに黒い飛沫
- sun-burst
- Inverness green
- Cardinal red
- Pelham blue
- silver burst
- gold burst
おまけ:70s 純正ハードケース【ロケットケース/チェーンソーケース】
“The Paul”には、通称「ロケットケース」「チェーンソーケース」と呼ばれるレスポール専用の純正ハードケースが付属していました。
こちらもGibsonからアップグレード版が販売されており、正式名称は「プロテクターケース」のようです。(2025年時点)
ノーリン期のプロテクターケースには2型あり、グレード(価格)による仕様の違いで分けられています。
当サイトでは便宜上、手触りのイメージから、低価格版を「ロケットケース」、上位版を「チェーンソーケース」とします。
レトロとも近未来的ともいえない独特な形状は、70年代Gibsonの個性を象徴するアイテムの1つとしても、たいへん魅力的です。
「ロケットケース」
今回付属のケースは低価格版「ロケットケース」

ウレタンのように少し柔らかい素材で作られており、一体成型で幅広のラッチロックが特徴です。

「ロケットケース」は長期的にみると消耗品らしく、ラッチの爪がヘタってくるとロックが効かなくなるようです。
ネックレストの黒い部分は小物入れになっています。
この個体の内張りは赤のモールド。

“Gibson”ロゴがエンボスで入れられています。
「チェーンソーケース」
参考までに上位版「チェーンソーケース」も。
後付けでなければ80年製のギターに付属していました。
チェーンソーケースは、「ロケットケース」に比べて一回り大きく、材質も硬くなっています。

内張りは青でした。
ラッチロックも金属製に変更され、より堅牢になっています。
それなりに使用感もあるので表面はヤスリのようにザリザリしていて、お世辞にも手触りが良いとは言えません。
先ほど「ロケットケース」はロック機構が弱点のように書きましたが、実はこの写真のチェーンソーケースはラッチの金具自体が1つ紛失しています。扱い方ひとつで簡単に物は壊れます。
当時の木製ケースに比べて防御力は申し分なく、ハードケースとして正解かもしれませんが、重い・硬い・大きい・分厚い、肌触りが悪い、など手持ち運搬するには不向きな点が目立つので、個人的には「ロケットケース」のほうが扱いやすく好みです。

ロゴは別プレートで、本体に接着剤で貼られています。
最後に:『剛毅木訥、仁に近し』
以上が、私の紹介した「Gibson“The Paul”」の詳細です。ちゃんとポイントは回収できていたでしょうか?
- 薄い塗装
- 理想的な重量
- 厳選された木材
- 材を活かすピックアップ
長々と書きましたが、結局のところ、自分の理想の音・理想の楽器を決めるのは、自分自身でしかありませんし、個体差のある製品の評価はその個体にのみ適用されるものです。
思い込みの設計思想であれ、ニッチな音響特性であれ、私は“このThe Paul”を抱えると、ふとした瞬間に垣間見える「昼行燈のしたたかさ」に安心感を覚えます。
たったそれだけです。
ここまで書いてみてわかったことは、私が“このThe Paul”を好きな理由は語り尽くせないほどあったにせよ、「銘器のひとつ」とする理由は、意外と上の一文だけで完結してしまうということです。
伝統の先に革新があるのか、そもそも革新的な伝統だったのか、Gibson社のことはわかりません。
希少個体・不人気機種・アタリの個体・間違いなく検品漏れ。
ノーリン期に関わらず、企業に関わらず、特定の時代に関わらず、製品である以上少なからず色々あると思います。
「何を以て“vintage”か?」の言及は避けますが、“楽器”として即戦力となり得る“vintageの資質”を“The Paul”は秘めていると私は考えます。
孔子の教えに「剛毅木訥、仁に近し」とありますが、私が“The Paul”にもつ印象は正にそれです。
S©ALETONE.のひとりごと:『巧言令色、鮮し仁』
『剛毅木訥、仁に近し』の対とされる言葉に『巧言令色、鮮し仁』があります。
自戒の念を込めて。
このブログも“他人の意見”ですので、真に受けず、暇潰し程度で、ご放念いただけると幸いです。
ギターはほぼ自己完結できる趣味です。自分の理想の楽器、理想の音を求めればそれでいいと思います。
プレイヤーであれコレクターであれ理想に出会うことができればそれは素敵なことです。
もし最後まで読んでくださった方がいらっしゃるのなら感謝申し上げます。ありがとうございます。
【広告欄】Gibson The Paul / The SG / The paul 2
生産終了から40年。
ウォルナットボディの“Standard”ですら最近では見かける機会も減ってきました。
“Firebrand” や “Deluxe” ですらお目にかかることは滅多に無く、その他カラーバリエーションに至っては、今となっては実在したのかさえ自分の記憶が疑わしくなってくる始末。
The SG
姉妹機種“The SG”
The Paul 2
薄胴のレスポール・スタジオといった趣の “The Paul 2”
広告欄
※このリンクにはアフィリエイトが含まれています。内容の確認はしておらず、紹介や推薦を目的としたものではありません。

ご利用いただくことで、運営のささやかな支えになります。判断はご自身の意志でお願いいたします。